連歌・俳諧の研究―桃山時代の和漢聯句
深 沢 眞 二
漢詩の一形態であった聯句と,和歌の上句・下句が鎖状につながっていって成立した連歌とが混ざり合うことで,和漢聯句(より古い呼称としては「聯句連歌」ないし「連句連歌」)の形式が成立した。その時期は聯句と連歌が共存するようになった平安時代後期にまで遡れそうであるが,鎌倉期以後に連歌が文芸としてより早く充実を見た過程で,和漢聯句においても連歌のほうの規則や手法が優勢のうちに展開した。やがて1500年代に至って,策彦周良という作者の出現によって聯句の権威が上昇し,並行して聯句の性格が連歌的な運びを含むものへと変わっていった。そうした聯句のがわの事情の変化によって,和漢聯句も作られやすくなり充実の時期を迎えた。それは,和漢聯句における聯句の権威が回復してきた過程と捉えることもできよう(注1)。
そうした和漢聯句史をよく反映しているのが,和漢千句の構成の変化である。
室町期の懐紙の表記に従えば,第一句が和句(いわゆる発句),第二句(いわゆる入韻句)が漢句という順に始まる場合を和漢聯句,逆に,第一句が漢句(いわゆる第唱句ないしは破題句),第二句(いわゆる脇句ないしは入韻句)が和句という順に始まる場合を漢和聯句と呼ぶ。こうした狭義の和漢聯句と漢和聯句とを区別して使うこともあるが,広義には両者を総称して和漢聯句と呼
そして,連歌に百韻×十巻の「千句」という形式があることに倣って,和漢聯句にも和漢千句がおこなわれる場合があった。たいてい,面八句,一折り22句,二折り50句などの追加が付く。江戸時代初期までの,作品として残っている和漢千句のすべて,全10種を掲げ,イロハ・・・・の符号を付し,十巻と追加の構成を見よう。白い□で狭義の和漢聯句を,黒い■で漢和聯句を示している。
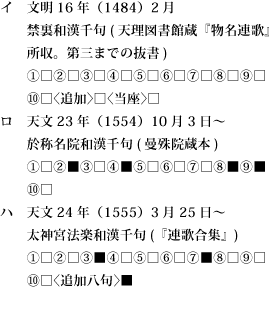
- 1 -