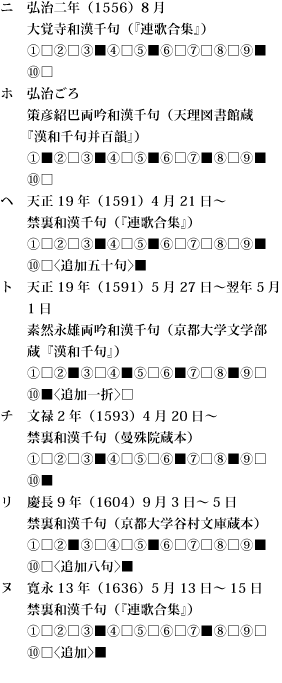
黒い■が多い程,聯句のがわの人々が尊重されているものと解される。文明16年(1484)のイはすべて白い□,つまりすべて和漢聯句である。当時すでに漢和聯句の例があるので,それは漢和聯旬の形式自体が成立していなかったせいではない。イの和漢千句の場には,聯句作者を立てて
以下順を追って見てゆくと,イとロのあいだには大きな時問の隔たりがあり,ロからリまでは50年間の幅にまとまっているのだが,ロ以降の時期にはもう,千句+追加のうちに最低でも3巻は漢和を行なうことが定例となっている様子が見て取れる。また,ホとトは,和句・漢句作者各1人が作った両吟和漢千句で,そのために和漢と漢和が交互に,均等に行なわれているのである。
このように和漢千句の内に漢和聯句の割合が増えていったことは,和漢聯句という文芸における聯句の地位が向上していったことを よく示していると思われる。
二
さて,桃山時代の堂上の和漢聯句ではすでに,ヘトチに見られる通り,五山の禅僧たちをはじめとする漢句の作者と,公家たち和句の作者とが,文芸的な意昧で拮抗して句を作っていた。桃山時代というのは一般的に,本能寺の変があった天正10年(1582)から,関ヶ原で西軍が負けて天下の覇権が徳川に移った慶長5年(1600)までを指す。それは,後陽成天皇の在位期間の前半にあたっている。後陽成天皇はたいへん学問や文芸が好き だったらしく,活字を作らせて儒学や日本古典の「慶長勅版」と呼ばれる書物の出版を行なったことで知られている。和歌や連歌の御会も盛んであった。
その,後陽成天皇のもとで,和漢聯句という特殊な文芸が実際どのような形で行われていたのかを記録類に見てみたい。
この方法は過去に小高敏郎氏が『近世初期文壇の研究』(注2)で用いたものである。同書においては,前述のへとトをめぐって,西洞
- 2 -