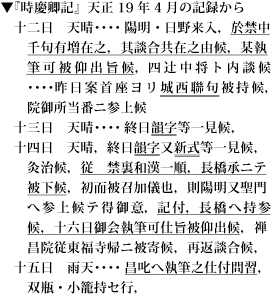
天正19年(1591年)の4月12日,時慶は陽明公近衛信輔(のちの信尹)と日野輝資の訪問を受けた。
禁中において千句のあらましこれ在り,
その談合どもこれ在る由に候,それがし
執筆仰せいださるべき旨に候
つまり,禁中で千句を開催することになったのである。これが前述のヘの和漢千句にあたる。灯ち合わせがあり,時慶が執筆(記録係兼ルールの点検
禁裏より,和漢一順,長橋殿うけたまわ
りにて下され候
とある。つまり,このときは,和漢千句そのものとは別に,前もって禁中で和漢聯句を一巻作ることになったのである。その予行演習的な和漢聯句を,「長橋」という人物の取り回しによって,一順すなわち参加者がひとめぐり回覧板のようにして付けていっている。時慶は初めてのことゆえに「陽明」近衛信輔や「聖門」聖護院門跡道澄に相談して了承を得てから,
記し付け,長橋へ持参し候
と提出した。すると,
十六日の御会の執筆,仕るべき旨仰せ出
だされ候
と,まずその予行演習の和漢聯句から執筆を勤めるようにと命じられたのである。時慶はどうやら自習だけでは心もとなく思ったようで,15日になると,
昌叱へ執筆のしつけ,問い習う
こともしている。職業連歌師である里村昌叱に,執筆の作法のレクチャーを受けたのである。このあたり,公家が頼りにすることで連歌師が力を得て行くことの具体的な一例で,当時の連歌師の役割をよく示していると思 う。
- 3 -