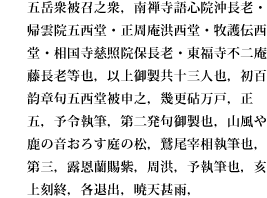
閏8月の22日に,秀賢は,
来月上旬のころ和漢御千句有るべき御沙汰
を受け,さっそくその手配に携わることになった。まず禅僧への書状をしたため,24日には南禅寺語心院に直接出向いて「御千句義」を伝えている。26日は,
今日三百韵,和漢発句一巡等これを定めらる
とあって,前述の(へ)直前の天正19年4月16日の和漢御会と同様,予行演習の和漢聯句が興行された。ついでにこの日,千句の発句 を誰が詠み一巡をどのようにするかが決められた。この時の御試しの御会は,念を入れて漢和・和漢・漢和の順に三百韻で,秀賢は第一と第三の執筆を勤めている。日の出前から亥上刻(午後10時ぐらい)まで,ずいぶんな長丁場であった。大幅な世代交代を経たあとの連衆を相手に,11年ぶりに盛儀を復活させようとしている後陽成天皇の意気込みが伝 わってくるようである。
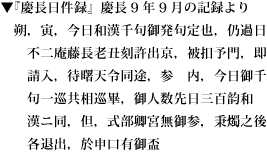
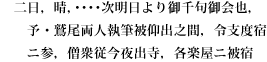
この時は千句当日の2日前,9月1日が発句定めであった。丑刻(午前2時ごろ)には東福寺不二庵から藤長老=集雲守藤が秀賢邸を訪れ,夜明けを待って一緒に参内している。2日になると,執筆の秀賢と鷲尾隆尚は支度のために自邸にかえったようだが,
僧衆は今夜より寺を出,おのおの楽屋に
宿らる
とある。「楽屋」がよくわからないが,僧衆は 雅楽の楽人の枠えの間に宿泊したということだろうか。
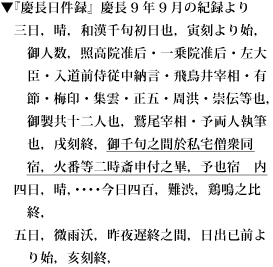
さて,和漢千句興行の3日間がやってきた。初日は寅刻(午前4時ごろ)に始まり,戌刻(午後8時ごろ)までにおそらく三百韻を終わっている。「御製共十二人」と,前月26日の予行演習の時より1人減っているのは,発句定めの日以来式部卿宮が脱落したためである。
御千句の間,私宅において僧衆同宿,火番
等,二時斎,これを申し付け畢んぬ,予,内に
宿る
の記事によれば,期間中僧衆は公家の邸に泊
- 10 -