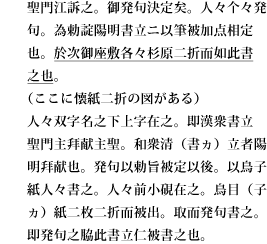
いっぽうの『鹿苑日録』では,18日にだけ上のような記録が残されている。その日は発句定めで,具体的な進行・作法に関しての詳しい記事が見出される。さすがに前回に比べて整然と執り行われているようである。発句を提出するさいの清書の仕方が,
おのおの,杉原二折りにて,かくのごと
くこれを書く也。
と図で示されているのは貴重である。
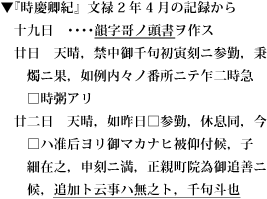
「韻字哥のかしら書き」とは,藤原定家以来,和歌の末尾に韻を踏んで作るという歌の作り方があり,そうした「韻字哥」を集めた本に,頭注を付けていったのだと思われる。 これも和漢千句に役立てるための勉強の一環であろう。このときの和漢千句は4月20日から22日までの3日間で行われた。
追加ということはこれ無しと,千句ばかりなり
と時慶は書いている。また,『時慶卿記』にしては珍しく,4月21日の記録が抜けていて,時慶はその日それほど忙しかったのだろうと推察される。
四
桃山時代という枠からははみ出すことになるが,後陽成天皇代のもう一つの和漢千句,慶長9年(1604)9月3日〜5日の御会(リ)の有様も見よう。この時には時慶は息男の時直に代替わりして禁中御会からは身を引いており,『時慶卿記』には「明日ヨリ和漢御千句禁中ニ在之由候(9月2日)」「禁中御千句初,和漢由候(9月3日)」としか書いていない。 また,『鹿苑日録』も記録者が有節瑞保から交替してしまっており,この和漢千句について触れるところは何もない。だが,舟橋秀賢の 『慶長日件録』に詳細lな記録がある。
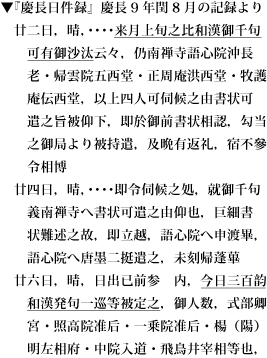
- 9 -