臨江斎へ発句談合に行く
とあるように,時慶は里村紹巴(臨江斎)のもとに発句の相談に行っている。この日の記録では『仮名遣』と『分韻』という2つの本について言及している。『仮名遣』は,仮名遣いの紛らわしい詞について使い分けを書き出した参考書,『分韻』は,漢和聯句用の韻字の字書を,特定の韻だけ分冊にして携帯用に拵えたもの(注4)ではないかと思われる。17日には聖護院道澄と紹巴に発句を見せて,紹巴から添削を受けている。また,『分韻』を書き写している。さらに,
発句ノ事に,紹巴まで切々行き候,玄仍
(紹巴の子)へも相尋候
と,発句の詠出にずいぶん苦心している様子が伺われる。
そして18日は例の発句定めがあって,第一から第十までの一巡を整え,亥刻(夜10時ごろ)に帰宅。時慶自身が発句を詠んだ第九の一巡について,こう書き留めている。
それがしの発句,弟九,哉の字これ在り,
兼勝卿灰タイ韻にて作る,哉の字,韻の
字なるゆえに,一折り程□も改む
つまり,結局発句定めによって時慶の発句は第九和漢の発句ということになったらしいのだが,「哉」という字を使っていた。ところが広橋中納言兼勝が,入韻句で「哉」の韻である灰冶韻を用いて句を作ってしまった。それでは差し合いになるので,一折り程,つまりすでにできていた一巡の和漢を,漢句が別の韻を踏むように添削した,ということである。
東京大学総合図書館竹冷文庫蔵の『連歌和漢集』という千句の抜き書きの資料によれば,時慶が苦心して詠んだ第九和漢の発句 は,
という句であった。なるほど,「かな」という切れ字が使われている。これは本来漢字で哉の字を書いていたと思われる。そうした場合,入韻句は,哉の字の韻,灰
近春梅影濃 廣中
(近き春,梅の影こまやかなり)
という冬韻を踏んだ句になっているが,この句がもともとは灰
近春濃影梅
というような,句末に「梅」が来る句形ではなかったかと想像できる。肝心なのは,このように,一巡が成った段階でも差し合いが見つかれば,韻を取り替えることも厭わずに, 部分的な修正を加えていたという点である。 御会の記録には完璧な作品を残す,という意志が感じられる。
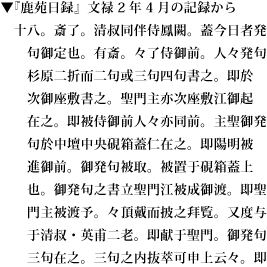
- 8 -