第三入韵の月字,山字に改正する也
と,その欠点を正すべく,有節の記録によれば原作で「霖晴月入紗(長雨が晴れて,月はうすものにくるまれているように見える)」となっていた句の,「月」を「山」に変更したというのである。また実際「霖晴山紗入」のかたちで伝わっている。
この『鹿苑日録』の記事からは,和漢千句が終わってからも差し合いがないか丁寧な点検が行われ,差し合いが発見されれば作者の意向に関わりなく修正が加えられたらしいこと,それに,その点検にはどうやら紹巴のような連歌師も協力していたらしいことがわかる。
三
続いて2年後の文禄2年(1593年)の,和漢千句(チ)をめぐる記録を見たい。
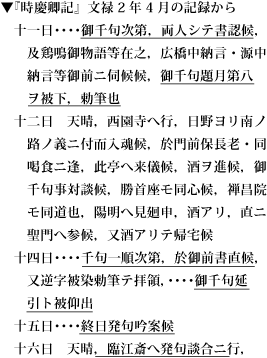
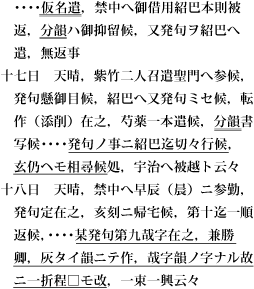
この千句にあたって時慶は準備段階から活躍している。まず11日,
御千句次第,両人して書きしたため候
とあるが,この両人とは時慶と日野輝資の2人のことで,和漢千句の構成を後陽成天皇の指図のもとに一晩がかりで書き出したのである。
御千句題月第八をくださる,勅筆なりとは,この千句では天皇が十巻の題を構成して自ら題を書き立てたもののようで,その第八の1枚をいただいた,つまり,時慶が第八の発句を詠むようにと命ぜられたのではないかと思われる。12月,時慶は日野輝資とのあいだで分担を決めて,千句の連衆を巡り 歩き和漢千句について報せてまわっている。
14日,
御千句一順の次第,御前において書き直し候
という作業があったが,どうしたわけか,急 に後陽成天皇は,
御千句延引と仰せ出だされ
て,千句が日延べになってしまった。
15日,時慶は,
終日発句吟案候
- 7 -