主聖より厳命有り,日はいまだ夕陽の際
なり,いま百句つかまつるべし云々。
と申し渡され,夜更けまでかかってもう一巻作る次第となった。翌22日は300句が作られた。時慶は初日より早く,有節は遅く出仕している。この日は初夜過ぎに終わった。最終日23日,追加の巻を合わせて350句を作っている。めでたい雰囲気の内に天皇は常の御所に帰り,宴会になった。有節は酔っぱらって相国寺に帰り,「横眠倒臥のみ」つまりたちどころに眠ってしまったと書いている。
時慶は翌々年,子息時康(のち時直)への庭訓の書『夢後記』(注3)において,この和漢千句で執筆を勤めたことを次のように書いている。
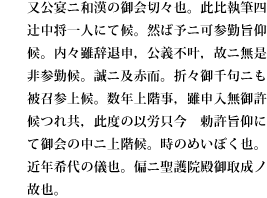
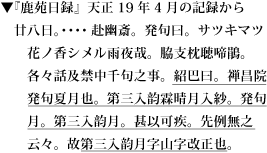
存節はその日,細川幽斎を尋ねた。発句と脇の応酬があり,話は禁中の千句の事に及ん だ。
紹巴いわく,禅昌院の発句は夏の月なり。第三
の入韻は「霖晴れて月紗に入る」,発句の月,
第三の入韻,月。甚だ以て疾とすべし。先例こ
れ無し。
細川幽斎の所に連歌師の里村紹巴が来合わせていた。そして禁裏千句のことについて批評 を始めたのである。
国会図書館蔵『連歌合集』の,この和漢千句の記録では,第三漢和聯句が,
(第唱句) 天夏月秋色 有和 (禅昌院)
(入韻句) 夕ぐれすゞし松風の声 左人臣
となっており,第十和漢聯句が,
(発句) 風なきも木の下や先夕すゞみ
新大納言
(入韻句)霖晴紗入 有和
となっている。したがって,右の『鹿苑日録』の記事は,有節が記億ちがいして,「第十」と あるべきところを「第三」と書いたのではないかと思われる。紹巴の発言は,「禅昌院の有和が詠んだ発句は夏の月の句だった。ところが,別の巻,第三の(実際には第十和漢聯句の)入韻句に,同じ作者によって月が詠みこまれている。これは欠点とすべきである。こ んな先例はない」ということである。発句
- 6 -