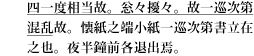
4月19日,時慶は,
禁中において□発句定めこれ在り
としか書いていないが,『鹿苑日録』には和漢千句の発句定めの様子がもう少し詳しく書き留められている。二日後に迫った和漢千句の十巻および追加の発句と,各巻の一巡とをあらかじめ決めておくのである。有節の記録によれば,天皇と門跡・摂家は座っているがその他の公家衆・長老衆は立たされたままでの作業であった。
御発句遊ばさる
これは「後陽成天皇が第一和漢の発句を詠まれた」ということだろう。
おのおの御発句等,紙二折りを引き合わ
せ,しこうして発句を,或いは三句或い
は二句書かれ,主聖に献じ,相定むる也
つまり,メンバーは2・3句づつ天皇に発句を提出し,天皇が千句の発句を定めるのである。追加を含めて11句の発句が決まると,鳥の子紙2枚2折りが配られてそれぞれ発句が書かれ,それからその場で11巻ぶんの,
一巡,書き立てこれ在り
という次第になった。ところがこの日には,
一巡,一人の前に或いは二,或いは三・
四,一度に相当たる故,
一巡次第混乱す
すなわち,一人の作者の前に複数の懐紙が同時にめぐってくるというような有様で,大混乱をきたしたのであった。そこで「一巡次第」を書立てたメモが懐紙の端に付された。結局 この日,夜半になってようやく連衆は解放されたのだった。
そうした準備があってからやっと,4月21日から3日間,和漢千句の当日を迎えたのである。
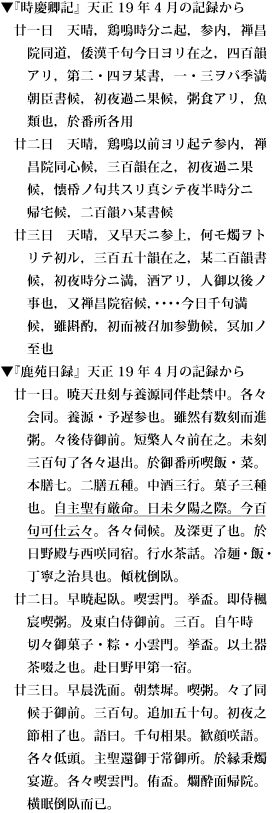
- 5 -