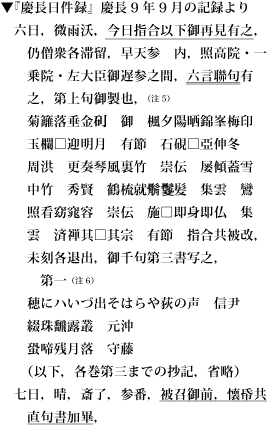
この和漢千句の場合には,3日間が過ぎてそれで解散,ではなかった。翌日,
今日指合以下御再見これ有り
ということがあって,僧衆はまだ禁中に留め置かれ,公家衆も早朝から参内したのである。興昧深いことに,遅刻者数名を待つ短時間に,「第上句(第唱句)御製」で僧衆および秀賢による「六言聯句」が行われている。秀賢は明経博士家たる清原家の出であり,自身も2年前に明経博士となっていた。儒家として和漢の漢方をつとめる秀賢が,禅
それからその日は指合(差し合い)の箇所が修正されて退出となったが,さらに翌7日には,
御前に召され,懐帋共,直に句,書き加え
畢んぬ
という。つまり御前で指示を受けて,和漢千句の懐紙に重ねての添削の筆を加えたというのである。前2度の和漢千句の時よりも,天皇のこだわりは高じているようだ。飽くなき情熱と言ってもよい。また,そのことが,興行の「難渋」(9月3日)につながり,終了時刻も毎夜深更に及ぶ事態を招いたものと想像される。
ちなみに,この和漢千句の和句の連衆の主力メンバーである中院入道前侍従中納言(通勝・素然)は,天正19年度と文禄2年度の和漢千句の際には勅勘を蒙って流寓の身の上だった。しかし彼は,天正19年5月から翌年にかけて泉州堺で雄長老英甫永雄(天正19年度・文禄2年度両方に出座した)と会し両吟和漢千句を興行,おそらくは禁裏御会に復する日を期して,和漢聯句の習得に怠りなかったと思われる。禁裏の千句は臣下にとってそれほどに晴れがましい嘉儀であった。ながらえて,このたび慶長9年度の和漢千句に加わり得たことに,中院通勝の感慨いかばかりであったことか。
なお,寛永13年(1636)5月13日〜15日の和漢千句(ヌ)は後水尾院の仙洞御会である。これについては田中隆裕氏「後水尾院の連歌活動について―江戸初期宮廷連歌の動向―」(注7)に言及がある。また,最近では,山田理恵氏「『後水尾院和漢千句』における固有名詞の特徴について―和漢聯句と和漢俳諧との比較―」(注8)がある。
- 11 -